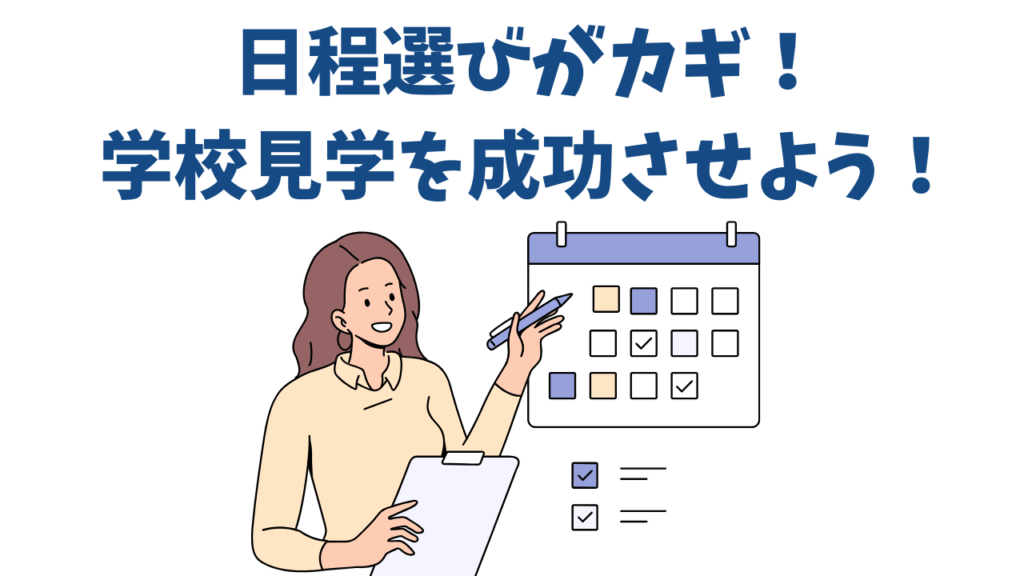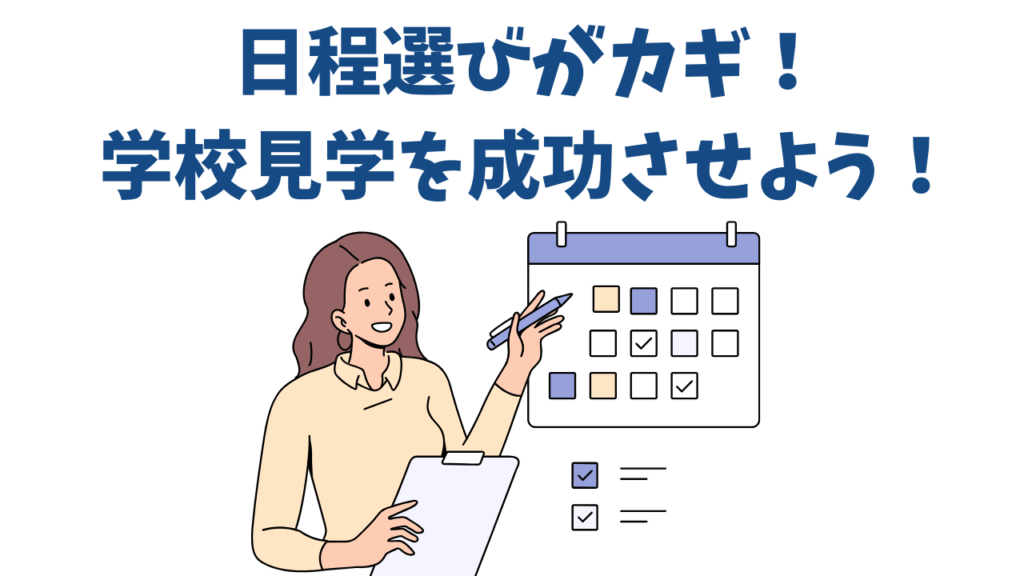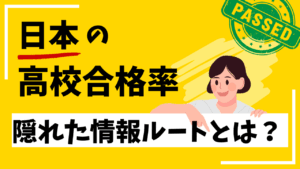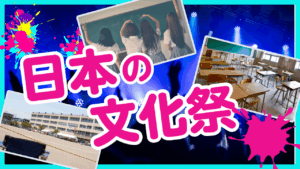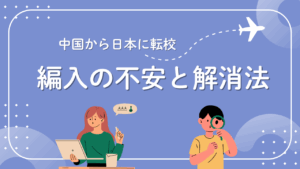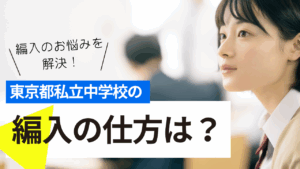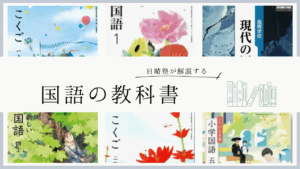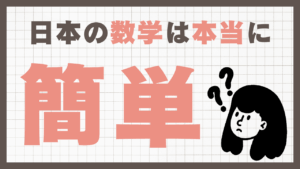中国国内とは異なり、子どもが日本で中学や高校に進学する際、見学(学校訪問・オープンキャンパス)は欠かせないステップです!
しかし、日本の学校見学には多くの細かい注意点があり、うっかりすると落とし穴にハマることも!
今回の記事では、詳細な見学攻略をまとめました。
見学のスケジュール、注意事項(やるべきこと・やってはいけないこと)、準備しておくべき質問リスト、よくある質問(QA)などなど、あなたの不安を解消して安心して参加できるようお手伝いします!
見学時期のスケジュール
春の見学(3月〜5月)
春は日本の新学期が始まる季節であり、多くの学校が新年度のスタートに合わせて見学会やオープンキャンパスを実施します。新入生が学校に慣れ始める時期でもあり、授業風景や部活動の雰囲気、先生や在校生の対応を自然な形で観察できる貴重なチャンスです。
また、春は気候が穏やかで、桜が咲く中での校舎見学は印象的な体験にもなります。初めての学校見学には特におすすめの時期です。
ポイント
✅ 授業の様子や生徒の生活をリアルに観察できる
✅ 校舎・施設の見学がしやすい
✅ 新年度の方針や学校のビジョンについて説明がある場合も
夏の見学(7月〜8月)
夏休み期間中に実施される見学イベントは「サマーオープンスクール」などと呼ばれ、学校側が特別なプログラムを用意するケースが多いです。実際の授業が行われていないため、在校生の姿は見られないこともありますが、その分、体験授業や部活動体験、個別相談コーナーなど、入試に向けたサポート型の内容が充実しています。
ポイント
✅ 模擬授業や部活動体験など実践的なプログラム
✅ 教職員とじっくり話せる個別相談が受けられる
✅ 自由研究や帰省と合わせてスケジュール調整がしやすい
秋の見学(9月〜11月)
秋は学校行事が最も活発になる季節です。特に文化祭(学園祭)の開催に合わせて見学できるのが大きな魅力です。普段の授業とは違った、生徒主体の活動を見ることができるため、学校の雰囲気や教育方針、在校生の人柄などを総合的に感じ取ることができます。
活気ある学校を体験したい場合は、秋の見学がベストシーズンです。
ポイント
✅ 生徒たちの主体性や創造性に触れられる
✅ 学校の雰囲気・カラーがよく伝わる
✅ 保護者同士の情報交換の場にもなりやすい
冬の見学(12月〜2月)
受験シーズンに近づくこの時期は、多くの学校が入試説明会や個別相談会を実施します。実際の入試に関する具体的な情報や、出願手続き、面接内容、過去問の配布など、実践的なアドバイスを得ることができる重要なタイミングです。
一部の学校ではこの時期にしか見学や説明会を行わないこともあるため、公式サイトなどで早めに日程をチェックしましょう。
ポイント
✅ 入試に直結する重要な情報が得られる
✅ 個別相談を通じて、志望理由書や面接対策も可能
✅ 一部の学校では予約枠がすぐに埋まるため早めの行動が必要
学校見学時の注意事項
必ずやるべきこと
1. 事前予約を忘れずに
多くの日本の学校、特に私立高校やインターナショナルスクールでは、事前にウェブサイトや電話での予約が必須です。予約なしで訪れても入れないことが多く、学校側にも迷惑をかけてしまいます。また、見学の定員に限りがあるため、人気校は予約開始後すぐに満席になることもあります。日程だけでなく、同行者の有無や参加人数も事前に確認しましょう。
🔹 アドバイス: オープンキャンパスの情報は学校の公式サイトやSNS(Twitter、Instagramなど)で早めにチェック!
2. 服装はきちんと整える
見学は学校にとっても「お客様を迎える場」であり、参加者の印象も評価の対象になることがあります。清潔感のある、落ち着いた服装(ジャケット、襟付きシャツ、ワンピースなど)を選びましょう。カジュアルすぎるTシャツ・短パン・サンダルなどはNGです。
🔹 アドバイス: 面接練習のつもりで、服装・髪型・姿勢にも気を配ると好印象を与えられます。
3. 時間には余裕を持って行動
見学会は定刻通りに始まります。少なくとも10分前には現地到着を心がけましょう。遅刻すると説明の重要部分を聞き逃したり、学校側にマイナスの印象を与えてしまう可能性もあります。
🔹 アドバイス: 地図アプリでルート確認、電車の遅延にも対応できるよう早めの出発を!
4. メモをとる準備をしておく
見学中は学校の説明、カリキュラム、進学実績、部活動、校風など、多くの情報が提供されます。ノートとペンを持参し、気になったことをその場でメモしておくと、後で志望理由書を書く際にも活用できます。
🔹 アドバイス: どの学校に何を感じたか、自分の言葉で記録するのがポイント!
絶対にやってはいけないこと
1. 無断での写真・動画撮影
学校によってはプライバシー保護や安全管理のため、撮影禁止エリアが多く設けられています。生徒の顔が映る教室内や、授業中の様子などは特にデリケートな部分です。写真を撮りたい場合は、必ず事前に許可を取りましょう。
🔺 注意: SNSに投稿する際は、許可の範囲を守ること!
2. 騒いだり、私語が多い行動を取らない
学校見学は他の参加者もいる共有の場です。大声で話したり、電話をしたり、子どもが走り回るなどの行為はマナー違反になります。携帯電話は必ずマナーモードに設定し、静かに行動しましょう。
🔺 注意: 特に保護者同士で話が盛り上がりすぎないよう注意!
3. 勝手に移動しない
学校が用意した見学ルートには、安全管理やプライバシーの観点からの配慮が含まれています。案内スタッフの指示に従い、立ち入り禁止の場所や教職員専用エリアに入らないようにしましょう。
🔺 注意: 子どもが単独で移動してしまわないよう、保護者がしっかり付き添ってください。
4. 挨拶・礼儀を忘れない
先生やスタッフとのあいさつは、見学の中でも大切なマナーです。入校時と退校時には必ず「こんにちは」「ありがとうございました」と笑顔で挨拶しましょう。丁寧な言葉遣いも大切です。
🔺 注意: 退出時には頭を下げてお礼を伝えるのが日本の基本的な礼儀です。
学校見学前に準備しておくべき質問リスト
1. カリキュラム・授業に関する質問
● 授業の進度はどのくらいですか?
中文:课程进度如何?
学校ごとに授業の進む速さが異なります。先取り型か、基礎を重視するか、授業の進度や内容のレベル感を確認しておきましょう。
● 外国人生徒への日本語サポートはありますか?
中文:有对外国学生的日语支持吗?
帰国生や外国籍の生徒への支援制度(日本語補習・別クラスなど)の有無や内容を具体的に聞くと安心です。
2. 進学・進路指導に関する質問
● 進学実績はどのようですか?
中文:升学成绩如何?
過去の進学先(高校・大学)や推薦の割合など、実績を具体的に聞くことで、学校の進学力が見えてきます。
● 進路指導はどのように行っていますか?
中文:升学指导是如何进行的?
定期的な進路相談や模擬面接、保護者との連携体制など、どのようにサポートされるかを把握しましょう。
3. 生活環境に関する質問
● 学校の安全対策はどのようになっていますか?
中文:学校的安全措施如何?
登下校の見守り体制、防災訓練、防犯カメラの有無など、安全への配慮がどうなされているかを確認しましょう。
● いじめ対策はありますか?
中文:有防止欺凌的措施吗?
いじめに対する相談窓口や対応フロー、学校全体での防止活動があるかを聞いて、安心できる環境かどうか見極めましょう。
4. 社団活動・部活動に関する質問
● 部活動はどのようなものがありますか?
中文:有哪些社团活动?
運動部・文化部・特別活動などの種類、活動の頻度、初心者の参加状況などを聞くと、子どもに合った環境かどうか判断しやすいです。
● 部活動の参加は必須ですか?
中文:必须参加社团活动吗?
参加が任意か、全員参加制かは学校によって異なります。入学後の生活リズムにも影響するため、重要なポイントです。
複数の学校を見学することの重要性
2024年に行われた株式会社DeltaXの調査によれば、高校入学前に保護者が見学した平均校数は約1.4校であり、約74%の保護者が実際に学校見学に参加していることが明らかになっています。
特に注目すべきは、複数の学校を見学した保護者ほど、「この学校を選んでよかった」と感じる割合が高いという点です。選択肢を比較することで、学校の教育方針・雰囲気・環境をより深く理解でき、子どもに合った進学先を見極めやすくなるのです。

実際に学校見学に行った保護者の声(調査より)
 保護者
保護者パンフレットやHPではわからなかった“空気感”を肌で感じられた



見学中に生徒同士のやり取りを見て、安心して預けられると思った



先生方の説明が丁寧で、信頼できる学校だと感じた



複数校を比較したからこそ、第一志望校の良さがよくわかった
見学校数が多ければ良いわけではない、でも…
もちろん、見学する学校の数が多ければいいというわけではありません。重要なのは、「子どもが自分の目で見て、納得できる学校に出会えること」です。そのためにも、事前に質問リストを用意し、学校側にしっかりと質問できる準備をしておくことがカギとなります。
日本の学校の見学は、学校の雰囲気や特色を理解するための絶好のチャンスです!事前に質問を準備し、マナーに注意し、見学後にはしっかりノートを整理すれば、比較・学校選びがしやすくなり、他のことも存分に楽しめます!