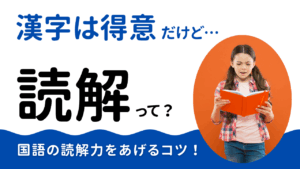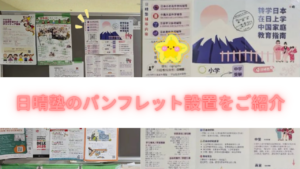日本に暮らす中国人家庭の中には、子どもが日本国内の私立中学校や高校への編入を目指して準備を進めているというケースが少なくありません。特に、国際的な経験を重視する家庭、あるいは日本語力を伸ばすために中学受験・高校編入に挑戦したいと考える保護者は年々増えています。
しかし、実際に進学を計画する中で、意外と大きな“壁”になるのが、
「編入までの数か月、子どもはどこで何をすればよいのか?」
という問題です。
たとえば以下のような状況がよくあります。
✅ 来日したが、次の私立学校の編入試験まで半年間ある
✅ 高校入試の準備に専念するため、学校に在籍していないまま過ごしている
こうした「空白期間」は、表面上は“受験の準備期間”に見えるかもしれませんが、実際には子どもにとって非常に不安定で、精神的・学習的な負担をともなうこともあります。
在日中国人家庭の多くは、教育に対する意識が高く、子どもの学力向上や将来の進路を強く意識しています。一方で、日本語力がまだ発展途中だったり、日本の学校制度に不慣れだったりすることで、以下のような課題を抱えやすい傾向があります。
✅ 空白期間中に学校に通わなければいけないのか分からない
✅ 住民登録はあるが、手続きが難しそうで不安
✅ 公立校に入れてしまうと、そのまま転校しにくくなるのでは?
✅ 子どもが孤立してしまわないか心配
「制度が分からないから何もしない」という形で、子どもが“教育から一時的に離れてしまう”リスクが生まれてしまうのです。
ような背景をふまえ、本記事では、制度的にできること・実際によく行われている対応・家庭が取れる工夫を具体的に紹介します。
「空白期間=何もできない時間」ではありません。
この期間をどう活かすかが、次の学校生活のスタートを大きく左右する鍵にもなります。
どうか安心して、ぜひ一歩を踏み出していただければと思います。
空白期間中に通える「学校」の選択肢とは?
私立中学校または私立高校への編入を目指している在日中国人の子どもが、編入試験の準備期間や合格発表を待つ期間など、いわゆる「空白期間」にある場合、「その間に子どもはどこで学ぶべきか」という問いに直面します。
このような空白期間においても、制度上は子どもが在籍・通学できる学校や学習の場が複数存在します。それぞれの選択肢には条件や特徴があり、子どもの年齢や在留資格の状況、日本語力の有無などによって最適な方法は異なります。ここでは、公的制度に基づいた通学の選択肢を中心に、現実的に多くの家庭が選んでいる対応策をご紹介します。
義務教育段階:小・中学生の場合
日本では小学校・中学校が義務教育であり、外国籍の子どもであっても、住民票があり、保護者が希望する場合には公立の学校へ通学する権利があります。このため、たとえ将来的に私立中学校への進学が決まっている場合でも、その間の数か月間を地域の公立学校で過ごすことは制度的に可能です。
多くの自治体では、「一時的な在籍」や「編入前の仮通学」についても柔軟な姿勢を取っており、学校に直接申し出る、もしくは市区町村の教育委員会を通じて相談することで、短期的な在籍や教室参加が認められるケースが増えています。特に外国籍の子どもが対象の場合、日本語指導支援(JSL: Japanese as a Second Language)を受けられる制度が整備されている地域もあり、日本語に不安のあるお子さんにとっても安心できる環境が提供されることがあります。
高校生の場合:制度上の制限と現実的な対応
一方で、高校は義務教育ではなく、公立高校への途中在籍や短期通学は制度上非常に限定的です。多くの都道府県において、公立高校の「編入」は年に1〜2回の決められた時期にしか受け付けられず、その基準も厳格なため、「数か月だけ通わせたい」「私立高校の合格が決まるまでの間だけ在籍したい」といった希望には基本的に対応してもらえません。
そのため、高校段階における空白期間では、公立高校ではなく、より柔軟性の高い別の教育機関を利用することが主な選択肢となります。
その代表的なものが、以下のような選択肢です。
▶ 通信制高校への仮入学・単位取得
通信制高校は、全日制や定時制に比べて登校日数が少なく、自宅学習を基本とするスタイルのため、入学・在籍の柔軟性が高く、途中からの参加も比較的受け入れられやすい特徴があります。空白期間を使って基礎教科の学びを継続したり、高校卒業に必要な単位の一部を前倒しで取得したりすることで、学習の継続と精神的な安定の両方を図ることができます。
▶ 塾や予備校、民間教育機関の活用
編入や受験を控えた高校生の場合、空白期間を使って塾・予備校などの学習塾に通い、集中して学力を高めるという選択肢をとる家庭も多く見られます。最近では、外国籍の生徒向けに日本語指導と主要教科を同時に学べるコースを設けている塾や専門校も増えており、進学準備をしながら語学面の補強も行える環境が整ってきています。
私立学校による「仮在籍」や柔軟な受け入れ体制について
空白期間の過ごし方について検討する際、意外と見落とされがちなのが、編入予定先の私立学校に対して直接相談を行い、編入前から一定の学習機会を得られる可能性があるという点です。
特に、すでにその学校への編入が内定している場合や、入学試験合格後に入学時期まで期間が空いてしまうといった状況では、私立学校が個別の事情を考慮して“仮在籍”や“早期受け入れ”を検討してくれるケースも少なくありません。
公立校の場合、在籍や転入には自治体の定める規則が存在し、それに沿って厳格に対応されるのが一般的です。それに対して私立学校は、学校法人ごとに運営されているため、校長や教頭の判断により柔軟な対応があるという特徴があります。
たとえば、以下のような対応が実際に取られることがあります。
このような「特別措置」は、公式にウェブサイトや募集要項に記載されているわけではないことが多く、保護者が直接問い合わせてみない限り、その可能性を知ることはできません。
このような柔軟な受け入れが実現すれば、子どもにとっては以下のような大きな利点があります。
「仮在籍」や柔軟な受け入れ体制の利点とは?
✅ 新しい学校環境に事前に慣れることができる
✅ 学びのリズムを維持でき、空白期間による学力低下を防げる
✅ 教員や同級生と交流する中で、安心して入学を迎えられる
また、保護者にとっても、「この学校を選んでよかった」と思える安心感や、「将来のトラブル回避」という実利的な側面もあります。子どもが新学期に急に学校に馴染めず不登校になってしまう、といったリスクを未然に防ぐ効果もあるのです。
空白期間の家庭での過ごし方は?
過ごし方①:公立学校への一時的な通学
義務教育段階の子ども(小・中学生)であれば、住民登録がある限り、短期間でも公立学校に通うことが可能です。すでに私立校への編入が決まっている、あるいは受験予定であっても、「それまでの数か月間だけ在籍させたい」と学校や教育委員会に相談すれば、多くの自治体では柔軟に対応してくれます。
この選択の最大のメリットは、日常のリズムを維持しながら、日本語環境に身を置けることです。学力に加えて、対人関係や日本社会での振る舞いといった“非認知的スキル”も自然に身につけることができるため、特に帰国後間もない子どもには効果的です。
注意点としては、正式な「転入学」ではなく「一時在籍」となるケースもあるため、通知表や成績の評価が出ない可能性や、教材や学用品を家庭で一部負担する必要があることなど、あらかじめ確認しておくことが大切です。
過ごし方②:塾・予備校・学習支援教室への通学
空白期間を有効活用し、編入試験や入学後の学習に備えて集中的に勉強したいという家庭には、学習塾や予備校の利用がおすすめです。近年では、外国にルーツを持つ子ども向けに設計された多文化対応型の学習塾も増えており、日本語指導と主要教科の学習を同時に受けることができる環境も整いつつあります。
また、地域によっては、NPO法人や教育支援団体などが運営する「外国人児童・生徒向けの学習支援教室」も存在します。こうした教室では、学校の宿題サポートや日本語指導、進路相談なども行われており、家庭の経済状況に応じて無料または低価格で受講できることもあります。
過ごし方③:家庭学習+オンライン教材の活用
公立学校への通学や塾の利用が難しい場合でも、家庭内で学習リズムを維持し、生活を安定させるための方法は複数存在します。たとえば、以下のような学習環境を組み合わせることで、子どもの自主性を育みながら、学力も確実に伸ばすことが可能です。
さらに、最近では、外国籍の子ども向けに開発されたAI学習アプリやオンラインプログラムも登場しており、時間や場所を問わず、学習の機会を確保することができるようになっています。
在留資格や行政手続き上の注意点
空白期間中の過ごし方については、学校や家庭内の学習環境だけでなく、在留資格(ビザ)や行政手続きとの関係にも十分注意を払う必要があります。これは、とくに長期間にわたって子どもが正式な教育機関に所属していない場合、将来的に在留資格の更新審査に影響する可能性があるためです。
「子どもが教育を受けているか」が審査対象になることも
在日外国人家庭の在留資格、特に「家族滞在」や「定住者」「日本人の配偶者等」などのビザを保有する場合、入国管理局は更新時に“本人および家族が日本国内で適切に生活しているか”という点を審査基準のひとつとしています。
その中で、子どもが学齢期にありながら学校に通っていない(=無就学)状態が長く続いている場合、以下のような懸念が指摘されることがあります:
もちろん、一時的な空白や家庭学習によって状況が説明できれば、問題とならないことがほとんどですが、その期間中にどのような学習支援を行っていたか、どのような理由で就学していなかったかを説明できるようにしておくことは非常に重要です。
行政への相談・連携でリスクを回避
もし「空白期間が発生しそう」「学校に通わせることができない時期がある」といった状況が事前に予測できる場合は、お住まいの自治体の教育委員会または市区町村役場に早めに相談することをおすすめします。
多くの自治体では、外国人の子どもの教育支援に関する相談窓口を設けており、以下のようなサポートを受けることが可能です。
行政のサポート体制
✅ 就学相談(どの学校に在籍できるか、どのような制度があるか)
✅ 日本語支援がある学校・教室の紹介
✅ 学習支援教室やフリースクールの情報提供
✅ 行政書類の作成サポート(日本語が不自由な場合)
また、自治体によっては、外国籍世帯向けに翻訳付きの案内資料や、多言語での手続きサポートを提供しているところもあります。こうした公的支援を活用することで、無用なトラブルやリスクを未然に防ぐことができます。
「通っていない」ことが問題なのではなく、「放置している」ことが問題
ここで強調しておきたいのは、子どもが一時的に学校に通っていないこと自体が直ちに問題になるわけではないということです。重要なのは、「その期間、どのように学び、どのように生活していたか」「保護者が責任を持って管理・支援していたか」が問われるという点です。
したがって、空白期間中に何をしていたかを記録しておく(例:学習記録、教材のリスト、出席した学習塾や活動の記録など)ことで、将来的な手続きにおいても安心して説明ができるようになります。
まとめ
子どもが日本の私立中学校または高校に編入するまでに生じる「空白期間」は、多くの在日中国人家庭にとって見えにくく、判断に迷う時間です。しかし実際には、制度的にも社会的にも、この期間を有意義に過ごすための選択肢は数多く存在しています。
まとめPOINT
✅ 義務教育段階の子どもであれば、公立学校に一時的に在籍することが可能
✅ 私立学校によっては、仮在籍や早期受け入れなどの柔軟な対応をとってくれる場合もあり
✅ 通信制高校や塾、学習支援教室など、家庭の状況に合わせた学びの場も選べる
✅ 保護者は、学力面だけでなく、生活リズムや子どもの心の安定にも配慮しながら、安心できる環境を整えていくことが大切
✅ 空白期間中の過ごし方は、在留資格の更新や将来の進路にも影響し得るため、行政との連携も忘れてはいけない
何より大切なのは、「学校に行っていないから」と焦ることではなく、その時間を“親子で将来に向けて準備する貴重な期間”として前向きに捉える姿勢です。たとえ制度上の制約があっても、柔軟な工夫と正しい情報によって、子どもにとって最善の道を選ぶことは可能です。
保護者として「一時的な不安」にとらわれすぎることなく、この空白期間を“成長の種まき”の時間として丁寧に過ごしていただければと思います。
日晴塾とは?
上記の問題を解決するため、ぜひ日晴塾をご利用ください!
日晴塾に期待できること
✅ 各教科の手厚い指導
✅ 日本語と母語のバイリンガル教師による授業
✅ 学校生活や進学に関するさまざまなサポート
✅ 子どものレベルに合ったカリキュラム設計
私たちは、日本に来たばかりの在日中国人家庭の小・中・高校生を支援し、安定して日本の学校生活に適応できるようにサポートします!