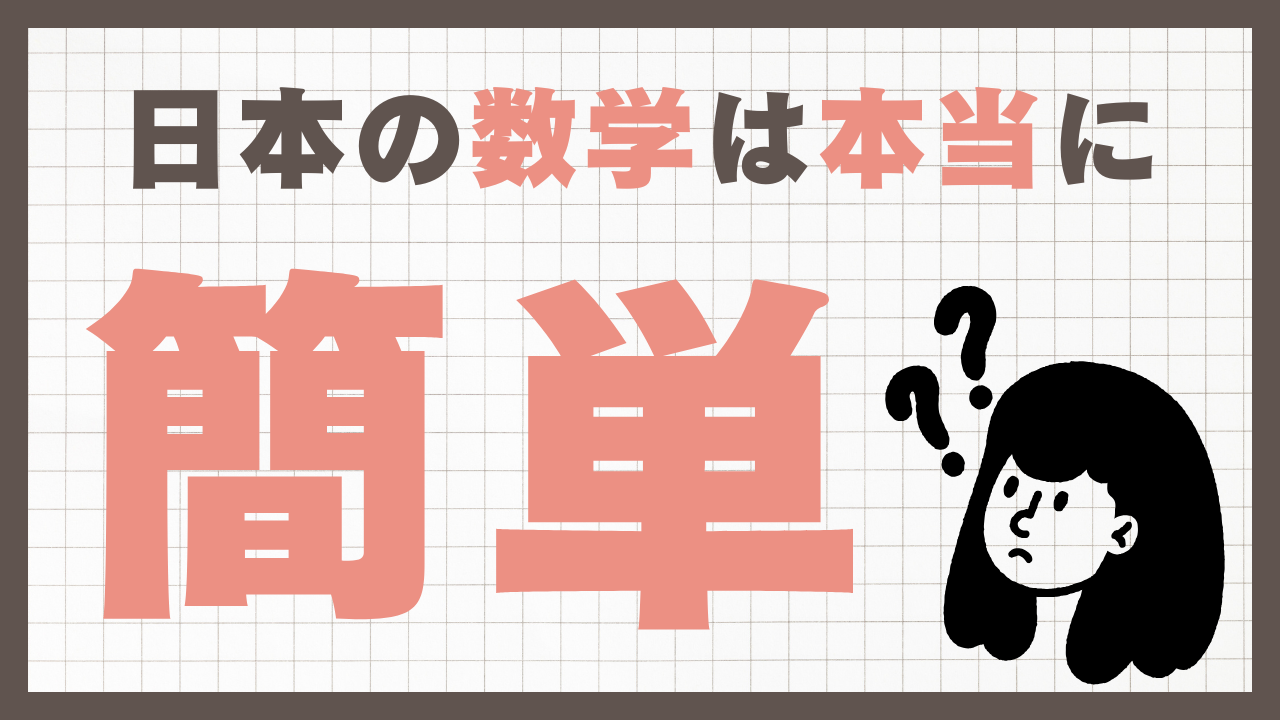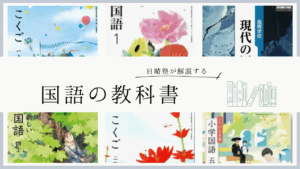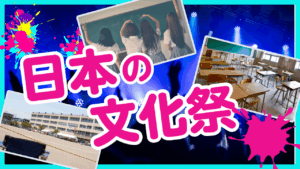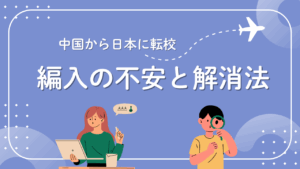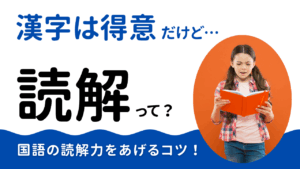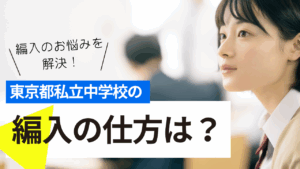以前の記事で、中国で数学が得意だった子が、来日後、つまずいてしまう4つの原因をお話しました。
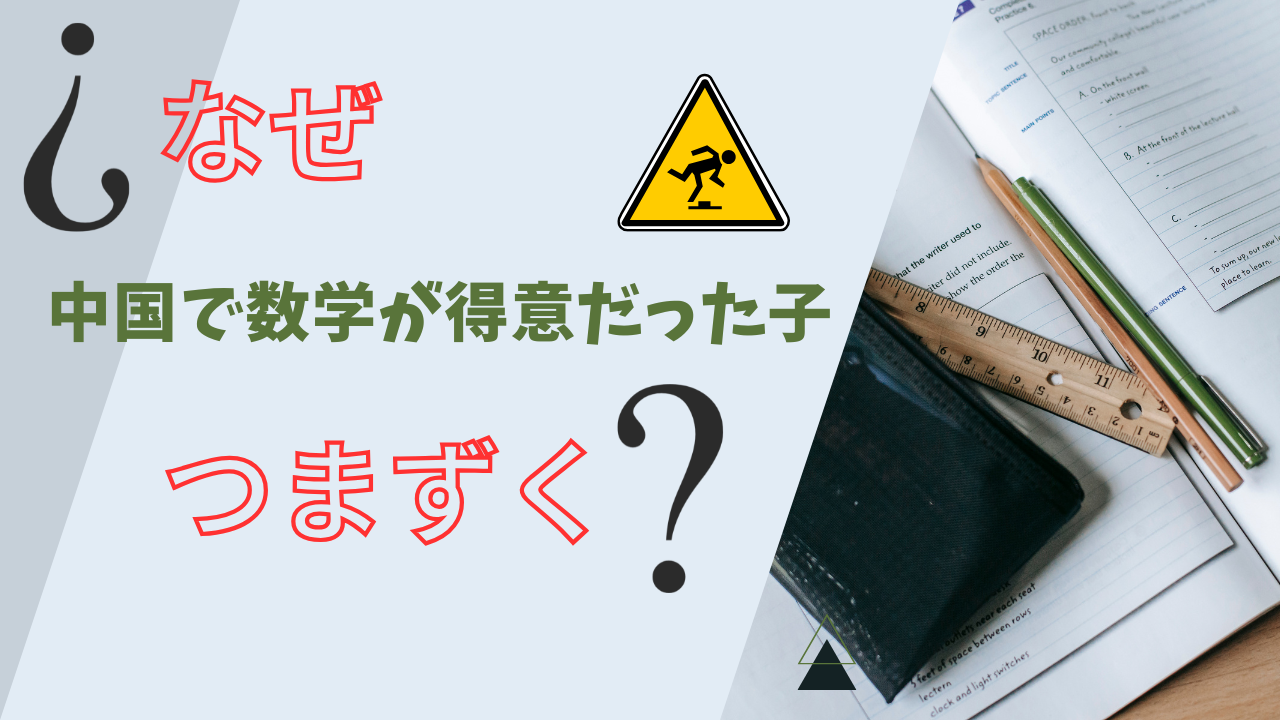
たとえば、日本語の問題文が読みづらい、日本独自の記号や出題形式に慣れていない――そのような点で戸惑い、実力が発揮できないケースもあります。
今回は、「日本の数学は簡単なんですか?中国の子どもはすぐにできるようになりますか?」というご質問にお答えします。

計算問題は簡単?でも“それだけ”ではない
日本の小中学校で扱われている基本的な計算問題は、中国の同学年と比較するとやや難易度が低めに設定されていることが多いです。
四則演算や分数、小数の計算、方程式の基礎といった内容において、中国ではより高学年向けの内容が早い段階で登場する傾向があるため、中国である程度数学に慣れてきたお子様にとっては、日本の問題が「簡単だ」と感じられることもあるでしょう。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
日本の数学では、「正しい答えを出す」だけでは評価されません。
「考え方の筋道」や「途中の計算式」、「説明力」が強く求められるのです。
たとえば、単純な文章題であっても、
こうした点が総合的に見られます。
中国では、「答えにたどり着く速さ」「複雑な計算を正確に処理する力」が重視されがちですが、日本ではその過程をしっかり示すことができなければ、たとえ答えが合っていても減点や不正解になることが少なくありません。
日本独自の出題内容と形式に戸惑うことも
さらに、日本の数学には独特の出題分野や形式が存在します。
確率や統計の問題
小学校高学年〜中学生の段階で扱われることが多く、グラフや表を読み取る力、データを整理・分析する力が求められます。中国ではこれらの内容を本格的に学ぶのは高校以降という場合もあります。
作図問題
コンパスや定規を使い、図形を正確に描く技術が求められます。問題文も長く、手順も複雑なため、日本語の読解力と図形感覚が両方必要になります。
図や図表を活用する文章題
国語的な読解力や日本語特有の表現(「〜より〜多い」「〜のうち最も〜なもの」など)を正確に読み取る力がなければ、数学的な処理以前に「設問の意味がつかめない」ということもあります。
このような出題に慣れていないと、「計算はできるのに点が取れない」という状態に陥りやすくなります。
見えにくい“言葉の壁”が、数学の理解を妨げる
「数学に言葉は関係ない」と思われがちですが、実際には日本の学校教育では数学も「言語を使って考える教科」として扱われています。
そのため、設問文の理解が不十分だと、たとえ計算力が高くても思わぬミスにつながってしまいます。
日本語には、あいまいさを含む表現や、複数の条件を含んだ設問が多く見られます。
あいまいさを含む表現
✅ 「すべて選びなさい」
✅ 「正しいものを2つ選びなさい」
✅ 「このときの考えとして適切でないものを選びなさい」
といった表現に慣れていないと、選択肢の読み違いや勘違いが起きやすくなります。
また、「次の問いにあてはまらないものを選びなさい」といった“否定文”が含まれる設問は、特に注意が必要です。
つまり、日本語の読解力も数学の点数に直結するということを意識しなければなりません。
日本の数学にスムーズに入るために必要な準備
こうした違いを踏まえると、中国から日本に来て学び始めるお子様にとって最も重要なのは、「内容のレベル」ではなく「スタイルの違い」に慣れることです。
「内容のレベル」ではなく「スタイルの違い」に慣れる
✅ 日本語の設問文に慣れておく(読解練習や設問解釈)
✅ 答えだけでなく「途中の考え方」をノートに書く練習をする
✅ 見慣れない単元(確率、作図、統計など)に少しずつ触れておく
✅ 日本語で自分の考えを表現する練習(説明問題への対応)
このような準備をしておくことで、「分からないから不安になる」状況を未然に防ぎ、安心して学習に取り組むことができます。

まとめ:違いを知ることで「苦手」を「得意」に変えられる
「日本の数学は簡単」という言葉には、ある意味で真実が含まれています。
計算そのものは、中国の高度な問題に比べれば、単純で基礎的なものが多いからです。
しかし、それをもって「簡単」と断じてしまうと、日本の学習スタイルの重要な要素を見落としてしまう危険があります。
数学も“文化の違い”が表れる教科であり、言葉・形式・価値観など、背景にある教育文化を理解することが不可欠です。
こうした違いを事前に知っておくことで、つまずきを避けることができ、さらにその違いを逆手に取って、自信をもって学習を進めることができるようになります。