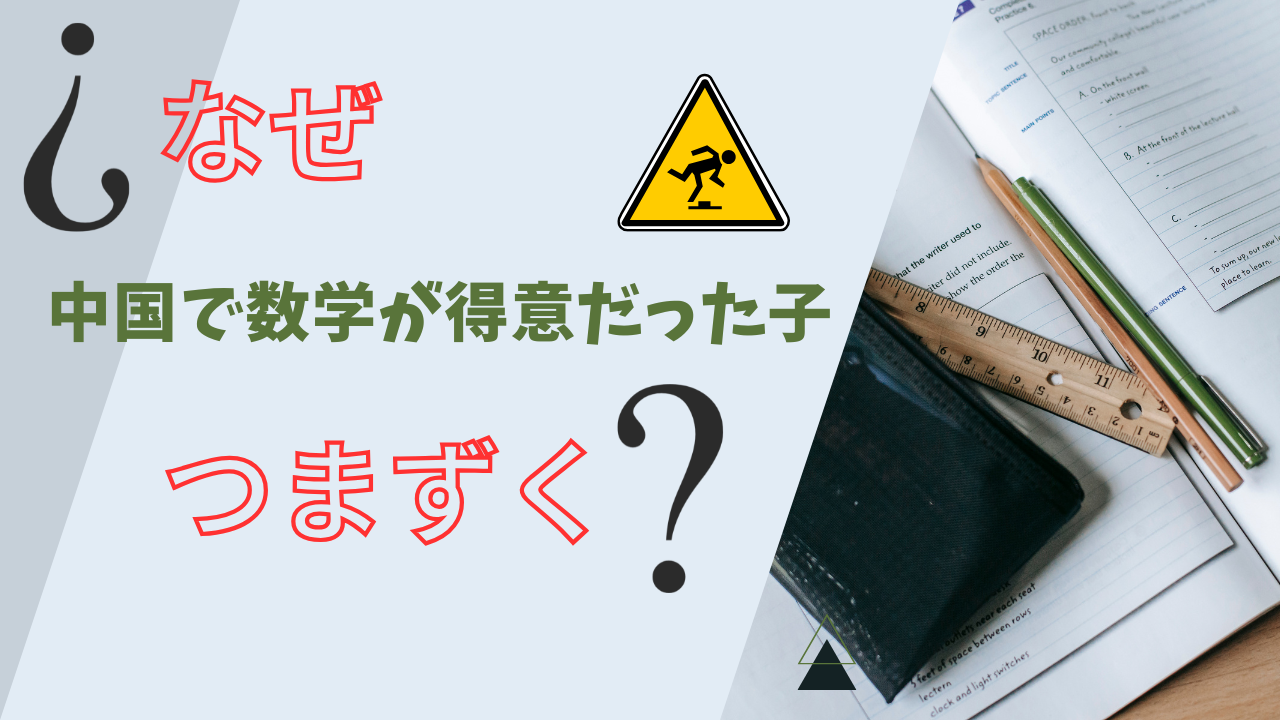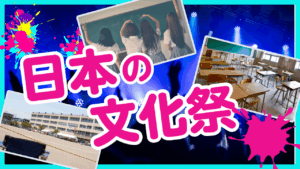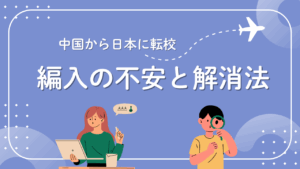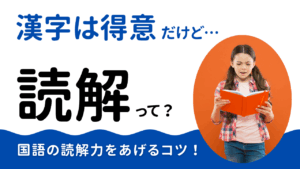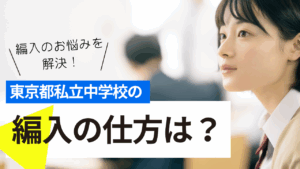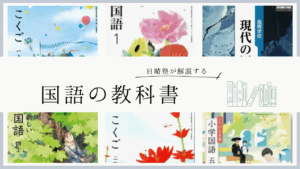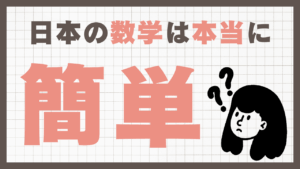今回の記事では、「中国で数学が得意だった子が、日本に来てから数学が苦手になってしまうのはなぜか?」という、多くの保護者さまから寄せられるお悩みについて、4つの原因をお伝えします!
日本語の壁
中国では成績が良いのに、来日すると点数が取れなくなる理由はいくつかありますが、まず大きな理由として、お子様の日本語力が関係してきます。
まず、お子さんの日本語力はどうでしょうか?
来日して間もない場合、日本語の文章を読むこと自体が難しく、問題文の意味がつかめずに、そもそも解くことができないというケースがよくあります。
日本の数学の問題文は、文章が長く、日常的でない日本語表現が多く使われているため、特に日常会話レベルの日本語しか習得していない段階では、大きなハードルになります。
実際に混乱するであろう、数学の問題例を挙げます。
上記の問題では、中国語と日本語で「以上」の意味が異なるため、「以上」という言葉の日本語の意味を正確に理解していないと解けません。
上記の問題では、数字が大きいものから書くのか、それとも小さいものから書くのか、答えは分かるのに、日本語の読み取りや書き方に苦戦すると解けません。
そのため、日本語の勉強だけでなく、数学の用語の勉強が必要になります。
日本の数学は「途中式・証明の記述」を重視する!
中国では、計算の速さや正確さ、そして最終的な正答が最も重視されます。そのため、途中の計算式や説明を省略しても、答えが合っていれば高得点になるのが一般的です。
一方、日本の数学教育では、「どうやってその答えにたどり着いたのか」という思考の過程や論理の組み立てが、得点の大きなウエイトを占めます。
また、日本では文章による論理的な証明が必須です。
- 仮定(与えられた条件)
- 論理展開(合同条件や定理の活用)
- 結論(求められた証明内容)
という順序で、文章で筋道立てて説明する必要があります。図だけで示したり、式だけ書いたりするのでは得点につながりません。
「したがって」「なぜならば」「ゆえに」「これより」などの論理をつなぐ日本語表現は、日本の数学記述において非常に重要です。
カリキュラムの相違
中国と日本では、数学で学ぶ内容そのものは似ていても、カリキュラムの順番が異なります。つまり、「どの単元をどの学年で習うか」が国によって異なります。
カリキュラムが異なることで起きる問題点
✅ 日本に来てから「中国ですでに習った単元をもう一度やる」ことがある
✅ 「中国ではまだ習っていない単元の続きがいきなり始まる」こともある
対策:学年にとらわれず、「単元ごとの確認」を!
このようなズレを埋めるために最も大切なのが、来日後すぐに
単元ごとに学習履歴を確認し、まだ習っていない単元については、学年をさかのぼって復習することが必要不可欠です。
学年にこだわらず、「理解していない部分に戻ってしっかり積み上げる」ことが、成績向上への近道です。
学年のずれ
もうひとつ見逃せないのが、学年のずれの問題です。
中国では通常「9月入学」ですが、日本は「4月入学」。そのため、来日したタイミングとお子さまの誕生日によって、中国では中学1年生だったのに、日本では中学2年生として編入されるというケースが多々あります。

起こりやすい問題
学年がひとつ上がってしまうと、当然ながら学習内容も進んだものになります。しかし、実際には前の学年の内容(たとえば中1の関数や図形)がまだ終わっていないまま次のレベルに進んでしまうと、わからない単元が急増し、授業についていけず、成績が伸び悩む原因に繋がります。
これは本人にとっても強いストレスになり、「自分は数学ができないんだ」と自信を失ってしまうこともありますので、単に「日本の学年に合わせる」のではなく、本人の学習段階に合わせた支援が必要です。必要であれば「学年をまたいだ復習」「本人に合ったペース調整」が効果的です。
まとめ
学年や国による制度の違いで、「つまずき」はどうしても生まれてしまいます。ですが、問題をしっかり整理して、基礎から丁寧に見直すことで、“わかる”が増え、“できる”につながるのです。
ご家庭では「成績」や「学年」だけでなく、「今どこまで理解できているか」という視点でお子さまの学習を見守るといいでしょう。
保護者だけで全部対応するのは難しいため、そんな時は経験豊富なプロのサポートを活用するのがいちばんの近道です!塾を探している方は、日晴塾を是非、ご利用ください!在日中国人専用の進学専門塾です!